おはようございます!
【 Sax-Fan サックス・ファン 】 の瀬尾です。
相変わらず、ご無沙汰をしております。
すみません。
2ヶ月に1回の発行ですね。
それでは早速まいりましょう!

基本に帰れ!-2-
前号では、アンブシュアについて述べてきました。
その中で、
『アンブシュアの概念』
という言葉が出てきましたが、
今日は、そのことについて少し述べておきます。

『アンブシュアの概念』というのを、
かいつまんで説明させて頂きます。
アンブシュア embouchure という言葉は、
どうも、フランス語からきているようですが、
「入り口」という意味があるようです。
音楽の世界、楽器の演奏に関しては、
このことは、ほとんど手掛りとはなりませんが、
『アンブシュア embouchure 』とは、
狭い範囲で言えば、
“マウスピースを囲んでいる口の状態”
という風に言えます。
最低限の役割としては、
吐き出す空気の柱の圧力に耐え、
その流れを、
リードの振動にエネルギー変換する、
その環境を作ることです。
そして、
リードが振動するための
クッションの役割も果たしながら、
音量、音程、音色の土台となって支えています。
管楽器奏者の『体』も、
楽器の一部として機能していますから、
楽器と体を繋ぐ、接点でもあります。
但し、ただそれだけのことを
行っているのではありません。
もっと重要な働きが、
『コントロール・センター』としての役割です。
単に空気が漏れないようにしているだけではなく、
単にリードが振動するだけの状態を作っているのでもなく、
もっと大きな役割があるのです。
少し実験してみましょう。
マウスピースのできるだけ奥深くをくわえ、
音を出してみて下さい。
「べ~~」といったような、非常に下品な音がしますよね。
リードは、何の障害もなく自由に振動していますが、
決して音楽的な音とは言えない音がしています。
アンブシュアというのは、
リードが自由に振動できる状況を作りながらも、
しっかりとセーブされた状況を作って、
美しい音の基礎を作っているのです。
では、アンブシュアとして、
どういう状況を作る必要があるのでしょうか?
前号ですでに、その内の一つのポイントをお話しましたが、
ここからはまた次回ということで、
それまでに一度、
あなたなりに整理しておいて下さいね。
ではまた。。。
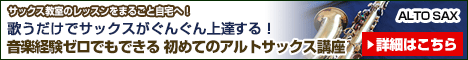
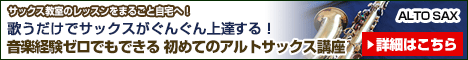
![[ Music-Life.biz ] 音楽屋支援サイト:音楽好きのあなたをサポート ~ 音楽でもっと豊かな生活](http://music-life.biz/parts/musicLifeBanner.gif)
![インターネット・ビジネス:稼ぐ仕組みを作り、マルチインカムで独立・起業を目指す! [ SeoKazuhiro.jp 瀬尾和弘グループ・メインサイト ]](http://seokazuhiro.jp/parts/seoKazuhiroJpBanner.gif)
![[ 瀬尾和弘グループ・ブログ部門 ] マルチインカムで独立・起業を目指すサイト構築法](http://seokazuhiro.jp/parts/seoKazuhiroComBanner.gif)
![[ 稼ぐ仕組みをインターネット上に作る支援サイト ] Gadget-Project ガジェット・プロジェクト](http://gadget-project.jp/parts/gadgetProjectBanner.gif)