おはようございます!
【 Sax-Fan サックス・ファン 】 の瀬尾です。
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
と、それにしても、
大変ご無沙汰をしておりまして、
申し訳ございません。
私の別サイト、
Gadget-Projectという、
インターネット・ビジネスのためのサイトなんですが、
そちらの方の絡みで、
ウェブ・サイトのプロデュースをしたり、
サイト作成のアドバイスをしたり、
そういう方面で忙しくなっていまして、
Sax-Fan に、なかなか戻ってこれずにいました。
すみません。
今号は、前号の続きで、
『ジャズのスタイル -2-』ということで、
早速始めたいと思います。

ジャズのスタイル -2-
前号は、
ジャズのスタイルを表す、それを分類した言葉として、
「○○・ジャズ」というのを拾ってみました。
分類された種類は多いんですね。
これらにおいての詳細は、
評論家等の方々の書籍等に任せるとして、
もっとざっくりとした部分で、
私なりに解説をしたいと思います。

Jazz ジャズは、
20世紀初頭の『Ragtime ラグタイム』という、
音楽スタイルに端を発して、
とか言われていたりすることもあるんですが、
Jazz ジャズの起源には色々な説がありますし、
そんなことはどうでもいいのですが、
少し、音楽理論的なお話をしますね。
Ragtime ラグタイムは“調性音楽”で、
Secondary Dominant セカンダリー・ドミナント
というのを、
この時期、すでに使われているのですが、
クラシックで言うところの、
『古典派』だと思って下さい。
本質的には同じ内容です。
そして、1910 〜 1920 年代、
Dixieland Jazz デキシーランド・ジャズ、
New Orleans Jazz ニューオリンズ・ジャズ、
と呼ばれるスタイルが、
ジャズの創成期として存在しているのですが、
その次の年代、1930 年代に流行った、
Swing Jazz スウィング・ジャズに至るまで、
ハーモニー的には、
それほど進化がないというか、
大きな違いはないんですね。
(映画『スウィング・ガールズ』に登場している曲は、
この、Swing Jazz スウィング・ジャズ
と呼ばれるスタイルの曲です。)
そして、ここからが面白いのですが、
1940 〜 1950 年代にかけて、
Be Bop ビ・バップというスタイルが始まるのですが、
Chord コードの扱いが、ガラリと変わってきます。
Charlie Parker チャーリー・パーカー
という、偉大なサックス奏者を中心に起こった
スタイルです。
オリジナルのコード進行も、
サブ・コードに置き換えられ、
Reharmonize リハーモナイズというのですが、
ざっくりと言うと、
コード進行に、様々な工夫をしていき、
それに基づいてアドリブを行なっていく、
そういうスタイルなんですね。
コード進行は、どんどん複雑になってきます。
Be Bop ビ・バップというスタイルは、
コードの流れが、
フレーズから聴き取れるようなフレージング、
そういうアドリブをやっていくのですが、
どんどんやっていくと、
“誰が演奏しても、
さほど変わりないんじゃないの?”
みたいなことになってくるわけです。
そしてそこから、それを打開するために、
今度は、
Mode モードという手法になってきます。
これは、教会旋法を基に、
ま、分かりやすく言うと、
ドレミファソラシド って“ド”が基準ですが、
“レミファソラシドレ”という風に、
“レ”を基準の音としたスケールに基づいて、
とか、
(これを、Dorian ドリアン と言います。)
“ソ”を基準の音に、
“ソラシドレミファソ”というスケールに基づいて、
とか、
(これを、
Mixo Lydian ミクソ・リディアンと言います。)
ほんとザックリとした言い方ですが、
そういうスケールを中心に考えて、
アドリブとかも組み立てましょうよ、
というスタイルなわけです。
“基準の音が違っても、
使ってる音が一緒だから、一緒じゃないの?”
と、チラッとでも頭をかすめた、あなた!
違うんですよ。
だって、短調って、
“ラ”の音を基準とした、
“ラシドレミファソラ”のスケールでしょ?
(これを、モード・スタイルでは、
Aeorian エオリアン と言います。)
存在できるコードが違ってきたり、
色々変わってくるんですよ。
そしてそして、
コードにガンジガラメになってきたのを、
解き放つ、別の考え方として、
それまでの既成の概念、
調性であったり、コード進行であったり、
様々な形式だったり、
そういった枠組みを外してしまいましょう、
というのが、
Free Jazz フリー・ジャズ、
( Free Form フリー・フォームとも)
ということになってくるんですね。
行き着くところまで行った感がありますが、
その後、
Post Free ポスト・フリー
フリー以降の時代として、
新しい発想を模索する時代になってくるんですね。
そういう流れで、
Jazz ジャズも変化していくわけです。
ジャズのスタイルに関して、
評論家のように細かく言っていても仕方がないので、
すっごい大雑把な説明でしたが、
大体のところ、こんなもんです。
お分かり頂けましたでしょうか。
ジャズのスタイルに関しては、
これで終わりにします。
(大雑把過ぎ? (笑))



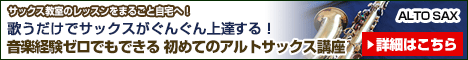
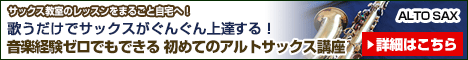
![[ Music-Life.biz ] 音楽屋支援サイト:音楽好きのあなたをサポート 〜 音楽でもっと豊かな生活](http://music-life.biz/parts/musicLifeBanner.gif)
![インターネット・ビジネス:稼ぐ仕組みを作り、マルチインカムで独立・起業を目指す! [ SeoKazuhiro.jp 瀬尾和弘グループ・メインサイト ]](http://seokazuhiro.jp/parts/seoKazuhiroJpBanner.gif)
![[ 瀬尾和弘グループ・ブログ部門 ] マルチインカムで独立・起業を目指すサイト構築法](http://seokazuhiro.jp/parts/seoKazuhiroComBanner.gif)
![[ 稼ぐ仕組みをインターネット上に作る支援サイト ] Gadget-Project ガジェット・プロジェクト](http://gadget-project.jp/parts/gadgetProjectBanner.gif)