■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--- Sax Fan --- サックス・ファン 『第16号』
2005年4月9日 テーマ 9小節目
──────────────────────────────
今号の本題 : 音の3要素
編集後記 : やりとり
──────────────────────────────
これから楽器を始めようと思っている人:じっくり読んでね!!
初心者・中級者:知らないネタがあるかも!!
しっかり復習しましょう!!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
おはようございます。
だいぶ暖かくなって、気分もHIに・・・。
何なんでしょうね。春のこのウキウキ感は。
単に欲情しているだけでしょうか?
となると、かなり動物並み・・・。
私の理性は・・・・???
私は、天候にしても敏感で、天気が悪いとダルダル・モードに入り
やすいので、注意が必要です。
世間一般で言われる様に、血圧が低いせいなのかなぁ。
確かに、上で100切ってますけど・・・。
一番最近で測った血圧が、59 - 95。
体温低め、血糖値も低めで、医者に、
「朝のこの時間に、よく起きて来ましたねぇ〜。」と言われたこと
も有ります。
医者が言うからには、やはり関係有るのでしょうか?
それは良いとして、これからの時期は、私にとって、活動しやすい
時期になってきます。
冬眠から覚めた変温動物の様に。
(やっぱりそういった動物レベル?・・・)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
このメルマガは、楽器演奏に興味はあるけど迷っている人・始めよ
うとしている人から、初心者、中級者を対象に書いていきます。
「それぞれ対象のレベルが違うのに、自分にとって有益な情報はあ
るの?」と思われる方がいっぱいいらっしゃることだと思います。
特に中級者の方は、「どうせ知ってること、できることばかりだろ
う」とお思いでしょう。
レベルは違っても、大事なポイントは一緒です。
そういった方は、もう一度チェックする意味で読んで下さい。
中には、知らなかったことがあるかも知れません。ほんのちょっと
のことでも、そこに、早くうまくなるためのヒントが隠れているか
も知れません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〔それでは、本題です。〕
──────────────────────────────
音の3要素
──────────────────────────────
1.pitch - 高低
音というのは、発音体となる物体が一定の周期で振動し、その振動
が空気の粗密波となって伝わり、耳に届くことで、音として捉えら
れるわけです。
その粗密波の振動数を、1秒間にどれだけ振動しているかを表した
のが「周波数」で、単位は「Hz」(Herz)ですね。
周波数の大きいものほど、高い音として聞こえるのは、ご承知の通
り。
2.loudoness - 大きさ
粗密波の振幅が大きくなればなるほど、大きな音となります。
〜 ←こういう形の波のグラフでいうと、「振幅」は、上下の高
さに当たります。
つまり、横軸の幅は変わらずに、縦軸方向に大きくなればなるほど、
大きな音として捉えられるわけです。
3.tone color - 音色
発音体の、材質や、それをどの様に振動させるかによって、音の大
きさや高低に関係無く、特有の音がします。
それが「音色」です。
波形で表すと、その形に違いが出ます。
その違いは何かというと、音の「倍音構造」の違いです。
楽器の音も、基音(fundamental tone)の他に、倍音(over tone)
をいくつも含んでおり、その倍音の、第何倍音が、どれ位の割合で
含んでいるかということが「倍音構造」ということです。
倍音構造が複雑になれば、波形が複雑になります。
人間の耳が捉える音として、
倍音構造の複雑な音は、「豊か」な音に聞こえ、
倍音構造の簡単な音は、「透明感」の有る音に聞こえます。
例を挙げると、バイオリンの音に比べ、フルートの音は、より簡単
な波形を示します。
なので、音に「透明感」を感じるのです。
ここで、奏者として勘違いして欲しくないことは、
倍音構造が より複雑 = より良い音
で有るかのように、単純に思ってはいけません。
確かに、倍音構造がより複雑であれば、情感のより豊かな音として
捉えられますが、あくまで、その楽器の特性を考えた上で、「音色
」の判断をしなくてはいけません。
サックスでいうと、良い音を出そうと単純に、倍音を出す練習をす
る人がいますが、それよりもまず、自分が求める「良い音色」を明
確にすべきです。
しっかりとイメージを作ることのほうが、余程大事です。
イメージを明確なものとすることで、自然にそれに近づいてきます
から。
さらに、倍音を出す練習をする時期が早ければ、正確なアンブシュ
アが判らなくなってしまいがちです。
正確なアンブシュアを崩してしまうことほど、愚かなことは有りま
せん。
「リラックス」した音を出すことを優先して下さい。
倍音を出す練習の方向性を間違えると、得てして、音が緊張しがち
です。
相当、あれやこれやとアンブシュアを変化させ、何が何だか判らな
い状態に陥って・・・。
そうなれば、リラックスどころでは有りません。
音が緊張していると、聞いている方は辛いです。
リラックスした音を出した方が、相手に訴える力が強いことを認識
して下さい。
すんなりと相手に入っていきますから。
倍音の練習等には、適正時期というものが有ることを忘れないで下
さい。
技術を上回った知識に振り回されると、遠回りすることになります
し、要らぬ悩みを作り出すことにもなりかねません。
------- ◇ ------- ◇ -------- ◇ ------- ◇ -------
音楽を説明するのに、どうしても抽象的になりやすい部分がありま
すが、できるだけ努力して、解っていただけるような説明を心がけ
てはいます。
しかし、私の力だけではどうしても足りないので、これを読んで下
さってるあなたに協力していただかなければなりません。
理解してやろうと、優しく力を貸して下さい。
よろしくお願いします。 m(_ _)m
なお、解らなかった点や、質問、感想等、なんでもいいです。
お気軽にメール下さい。
info@sax-fan.net
待ってます!!
------- ◇ ------- ◇ -------- ◇ ------- ◇ -------
──────────────────────────────
編集後記:やりとり
──────────────────────────────
インプロビゼーションのソロの最中、そこでは、色々なやりとりが
行われています。
ソロをとっているものが出すリズムに、ドラムが食い付いてきたり、
或いは無視したり。
複雑なコードで、ピアノが応戦したり・・・。
会話にすると、こんな感じです。
sax(以下 s):「ほらほら、どうだどうだ!」
drams(同 d):「それがどうした。知らないよ。」
piano(同 p):「そうだ。まだまだ。」
bass(同 b):「こっちは4分音符しか弾いてやるものか。」
s:「付いて来てくれよ〜。」
一同:「・・・・(無視)」
s:「よ〜し、昇りつめてやる。トレリラトレリラビヒャーッ!!」
一同:「(来た来た・・。でもまだダメ。)」
s:「トゥイララリララリズビドゥビラリロリ・・・・・・」
d:「これでも食らえ!! ドバブシッ!!」
p:「よし、総攻撃だ!! ギャギゴンガゴンガギゴゴン・・・」
b:「ントゥ〜ントゥントゥンビドドド〜ン・・・」
s:「(はぁ〜はぁ〜はぁ〜)負けてなるものか!! ピロリ〜〜
パラプピパラプピパヒィ〜プパポペポドゥウィ〜タトレリラ・
・・・・・・・・・・・」
・
・
・
・
・
お客さんを巻き込んだ戦場は、今日も夜がふけて行く・・・。
============================================================
最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。
ご意見・ご感想・ご要望等、何でも結構です。
お気軽にメール下さい。
info@sax-fan.net 瀬尾和弘
============================================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご感想 : info@sax-fan.net
■URL : http://www.sax-fan.net
■登録 : 《終了しました》
■発行 : Sax-Fan サックス・ファン 瀬尾和弘
Copyright(C) 2004 Sax-Fan, All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 |



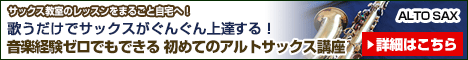
![[ Music-Life.biz ] 音楽屋支援サイト:音楽好きのあなたをサポート 〜 音楽でもっと豊かな生活](http://music-life.biz/parts/musicLifeBanner.gif)
![インターネット・ビジネス:稼ぐ仕組みを作り、マルチインカムで独立・起業を目指す! [ SeoKazuhiro.jp 瀬尾和弘グループ・メインサイト ]](http://seokazuhiro.jp/parts/seoKazuhiroJpBanner.gif)
![[ 瀬尾和弘グループ・ブログ部門 ] マルチインカムで独立・起業を目指すサイト構築法](http://seokazuhiro.jp/parts/seoKazuhiroComBanner.gif)
![[ 稼ぐ仕組みをインターネット上に作る支援サイト ] Gadget-Project ガジェット・プロジェクト](http://gadget-project.jp/parts/gadgetProjectBanner.gif)